FXでは様々な国のトレーダーがチャート分析を行っており、彼らの名前がつけられた指標が複数存在しています。
基本となる移動平均線を元にして改良を加えた指標もいくつかあり、その中の1つにポリジャーバンドがあります。
今回はポリジャーバンドについて、以下の内容に触れていきます。
- ポリジャーバンドとは一体何か
- ポリジャーバンドの使い方
- ポリジャーバンドの売買パターン
- ポリジャーバンド利用時の注意点
ポリジャーバンドについて調べていたのでしたら、この記事が役に立ちますので是非最後まで読んでみてください。
ボリンジャーバンドとは
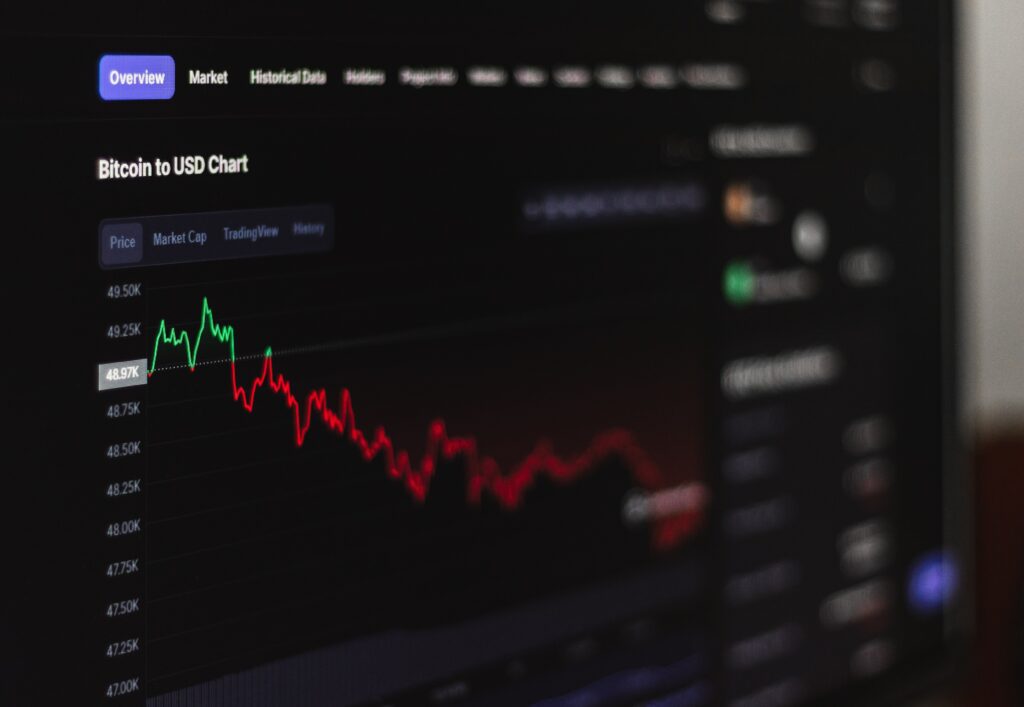
アメリカ人投資家であるジョンポリジャーが単純移動平均線を元にして考案したテクニカル指標が、ポリジャーバンドです。
単純移動平均線を元に、線の上に標準偏差と呼ばれるデータがどれぐらいばらついているかを表したバンドのことをポリジャーバンドと呼びます。
このポリジャーバンドのラインには、範囲内に価格が収まる確率が約68.3%の「±1α標準偏差」や、確率約95.4%の「±2α標準偏差」といったものがあります。
またバンドは価格の変動率自体を反映したものとなっていて、値動きがでかいとバンドが拡大し、値動きが小さめだと縮小するようになっています。
ボリンジャーバンドの使い方

ポリジャーバンドには一定の特徴がある以下のような4つの形状があります。
- スクイーズ
- エクスパンション
- バンドウォーク
- ポージ
形状は上記以外にも複数ありますが、上記は特にポリジャーバンドを使う上で覚えておいたほうが良い形状です。
ここからは、上記のポリジャーバンドの形状について順々により詳しくご紹介していきましょう。
スクイーズ
チャートに対して表示しているポリジャーバンドの幅が狭くなっていてもみ合い相場になっているところを、スクイーズと呼びます。
このスクィーズ形状になっている場所は、価格の変動率が低くなっていることを示しています。
相場が大きく変動しない状態になっているので、この形状のときに取引を行っても利益はあまり期待できない状況になっていることがわかります。
エクスパンション
スクイーズとは逆にポリジャーバンドのい幅が大きくなっている形状を、エクスパンションと呼び変動率が高くなっていることいを示しています。
相場が大きく変動しやすい状況になっているため、この形状の際に取引をすれば大きめの利益が期待できると言えます。
特にチャートのローソク足部分の終値が±2αラインを上に突き抜けたら買い、逆に同じラインを下に突き抜けたら売り注文すれば、より利益が出ると考えられます。
バンドウォーク
ポリジャーバンドの±2αラインに沿うような形でローソク足が並んでしまっている状態のことを、バンドウォークと呼びます。
チャート内のトレンドが一定の変動幅で続いていっている状態になっていることを示していますね。
並んでいるローソク足が+2αラインに沿っている時は上昇トレンド、-2αラインに沿っている時は下降トレンドになっています。
ポージ
表示させているポリジャーバンドの中でも、特別大きく幅が拡大している部分のことをポージと呼びます。
一番大きく価格が変動していた部分になっていることを示していますね。
このポージは価格変動が一番大きかった部分であると共に、トレンドがここで終了したことも示しています。
ポリジャーバンドの売買パターン

ポリジャーバンドの売買パターンとしては、以下の二通りがあります。
- 逆張り手法
- 順張り手法
株価が下がった底値狙いの逆張り手法とバンド拡大かつ株価急騰部分をねらう逆張り手法の2つです。
ここからは、上記ポリジャーバンドの売買パターン二通りについて、より詳しい説明をしていきます。
逆張り手法
ポリジャーバンドの特徴として、バンドの中で上下に変動しやすいといった点があり、これを利用して逆張りするのが逆張り手法です。
株価がバンドの下限にまで到達したら買って、逆に上限まで到達したら売るといった流れになります。
具体的には-2α近辺まで落ちてきたら底値での買い地点となり、逆に+2α付近まで登ってきたら高値での売り地点になるわけです。
順張り手法
バンドが収縮状態だとエネルギーを貯めている保ち合いになっており、ここから株価がバンド上限を突き抜けた場合、大変動する特徴を持っています。
これを利用すれば、株価急上昇初期状態の判別ができ買うタイミングを図ることが可能になります。
このような上昇トレンドになった場合に+1αに沿った上昇をするハンドウォークが発生するので、この状態になったら持ち株を保有し続けることで利益が伸びます。
具体的にはバンドが収縮状態時、株価が+2α(or+3α)を突き抜けたら買い地点となり、それ以降バンドウォークを経由して+1αを下回ったら売り地点となります。
ボリンジャーバンドを使う際の注意点

特に注意しないといけないのはポリジャーバンドの売買パターンを使う場合です。
標準偏差の値は、特定の過去データを元に設定した区間内での移動平均線で算出しているため、今後株価が絶対にそこの確率に収まるわけではないです。
なので逆張り手法を利用しても±3αを逸脱する可能性もあります。
順張り手法に関しても「ヘッドフェイク」と呼ばれている、昇ると見せかけて逆に下がっていく減少が存在しています。
売買パターンを使ったものの想定外の動きになってしまったら、損切りする必要性がでてくることを頭に入れておいたほうが良いです。
最後に

今回は単純移動平均線を元に考案されたテクニカル指標の1つである、ポリジャーバンドについてご紹介していきました。
ポリジャーバンドには特に特徴的な形状が4つあり、それらを元に過去にチャートがどんな動きをしていたかを分析していきます。
またポリジャーバンドには逆張り手法と順張り手法といった2つの売買パターンがあります。
売買パターンについては過去のデータを元にしているため、未来では必ずしもそのパターンの動きをするとは限らない点に注意が必要です。
ポリジャーバンドを利用していくのであれば、しっかりとした損切りラインを設定して大損しないように気をつけましょう。







コメントを残す