FXではチャート分析を行う際、様々なテクニカル指標を用いるのですが、大体の場合は2つ以上のテクニカル指標を組み合わせることが多いです。
数多く存在しているテクニカル指標の1つとして、ストキャスティクスが存在しています。
今回はそのストキャスティクスについて、以下の内容をご説明していきます。
- ストキャスティクスがどういったものなのか
- ストキャスティクスの見方について
- ストキャスティクスの使い方について
- ストキャスティクスとRSIの違いについて
- ストキャスティクスを使う際の注意点
ストキャスティクスがどういったものなのかを始め、見方や使い方など基本的なことをお教えいたします。
ストキャスティクスに興味があった人や、これから学んでみようと考えていた方は是非このブログを参考にしてみてください。
ストキャスティクスとは

ストキャスティクスは正式名「Stochastic oscillator」と言い、意味は「確率に基づいたオシレーター」というオシレーターの1つです。
1950年代アメリカのアナリストであったジョージ・レーン氏が開発したテクニカル指標で、過去一定時期の最高値・最安値を使って終値の水準を分析するものです。
「%K」「%D」「Slow%D」の三本線を使って0~100%までの数値を算出し、相場の加熱がどれぐらいかを示せるようになっています。
ストキャスティクスの見方

ストキャスティクスの見方としては、以下の二通りがあります。
- ファーストストキャスティクス
- スローストキャスティクス
ファーストストキャスティクス・スローストキャスティクスいずれも「%K」「%D」「Slow%D」の三本線のうちから、二本を使ってみていきます。
ここからは、上記のストキャスティクスの見方について、上から順番に詳しくご紹介していきます。
ファーストストキャスティクス
「%K」・「%D」の2本を使って見ていく方法がファーストストキャスティクスです。
対象となっている期間内の変動幅に対して、近々の価格がどういった場所にあるかを表す数値が「%K」です。
対象を一週間として、その中で近々の価格が一週間以内で一番高いと%Kは100%、逆に一番低いと%Kは0%になり、これをさらに単純移動平均化させたのが%Dになりますね。
この見方は価格に対して素早く反応しますが、あまりにも敏感すぎてダマシが多発するといったウィークポイントがあります。
スローストキャスティクス
「%D」・「Slow%D」の2本を使って見ていく方法がスローストキャスティクスです。
「%D」はファーストストキャスティクスにおける「%D」と同じですが、ここでは「Slow%K」と呼ぶこともあります。
%Kを移動平均化した%Dを更に移動平均化させたのが「Slow%D」となります。
この見方は価格に対して遅めに反応しますが、ダマシの発生率が低めな傾向を持っています。
ストキャスティクスの使い方

ストキャスティクスの使い方としては、以下の3つが挙げられます。
- ゴールデンクロス
- デッドクロス
- ダイバージェンス
買いサインとなるゴールデンクロス、売りサインとなるデッドクロスに加えて、ダイバージェンスという使い方もあります。
ここからは、上記のストキャスティクスの使い方3つについて順々にご説明させていただきます。
ゴールデンクロス
ゴールデンクロスはストキャスティクスだと、「%K」が「%D」を下から上に突き抜けた時になります。
特に売られすぎとなっているゾーン内でこのゴールデンクロスが現れると、買いのサインとなって価格が上がりやすくなります。
ゴールデンクロスが現れたとしても必ず価格が上がるわけではないですが、下落している価格が弱まった時にサインが出やすいので、流れの変動タイミングが把握しやすいと考えられます。
デッドクロス
デッドクロスはストキャスティクスにおいて、「%K」が「%D」を上から下に突き抜けた時になります。
特に買われすぎとなっているゾーン内でこのデッドクロスが現れると、売りのサインとなって価格が下がりやすくなります。
デッドクロスも現れたとしても必ず価格が下がるわけではありませんが、上昇している価格が弱くなった時にサインが出やすいので、流れの変化タイミングが把握しやすくなります。
ダイバージェンス
価格に対してインジケーターの変動が逆行する現象であるダイバージェンスは、ストキャスティクスにおいても発生します。
例えば価格のほうは切り下げる動きになっているにも関わらず、インジケーターとなるストキャスティクスは切り上げるような動きになったとします。
このようなダイバージェンスは価格が落ちる勢いが以前と比べて弱くなっており、トレンドの動きが変わる前兆になる可能性が高いです。
ストキャスティクスのダイバージェンスは利益発生中ポジションの利益確定・トレンド方向に新しくトレードの見送り検討などの目安に利用することができます。
ストキャスティクスとRSIは似て異なるもの

ストキャスティクスと同じオシレーター系指標であるRSIは、その性質上よく似ていると言われています。
ラインの形そのものが似ていますし、どちらも「売られすぎ」や「買われすぎ」を判断するために利用されることが多いです。
この2つは似ていますが異なっている点もあり、それは「売られすぎ」「買われすぎ」の範囲内かを判断するRSIに比べて、ストキャスティクスは売買のサイン自体を読み取ることができます。
紹介したように「%K」や「%D」といったラインを使い、そのクロスによってRSIよりも強い売買サインがわかるため、RSIより判断がしやすいオシレーター系指標となります。
ストキャスティクス利用時の注意点

RSIよりも売買の判断がしやすいストキャスティクスは、レンジ相場になっているとかなり有効なチャート分析法となります。
ですが、RSIなど他のオシレーター系指標と同じように、強めのトレンドが出てしまっている時は上下に張り付いて役に立たなくなってしまう点に注意が必要です。
また「%K」と「%D」の二本を使って見るファーストストキャスティクスにおいては、ダマシが発生しやすいといった点にも気をつけたほうが良いです。
まとめ

今回はオシレーター系指標の1つであるストキャスティクスについて、どういったものかを始め使い方や見方・注意点などをご紹介してきました。
ストキャスティクスでは重要となる「%K」「%D」「Slow%D」の三本線から二本を使って、相場が「買いすぎ」または「売れすぎ」の加熱度合いを見ることができます。
またストキャスティクス内でのゴールデンクロスやデッドクロス・ダイバージェンスといった使い方で、売買のサインを判断することができます。
ストキャスティクスは売買のサインを判断するためのオシレーター系指標として優れていると言っても過言ではないです。

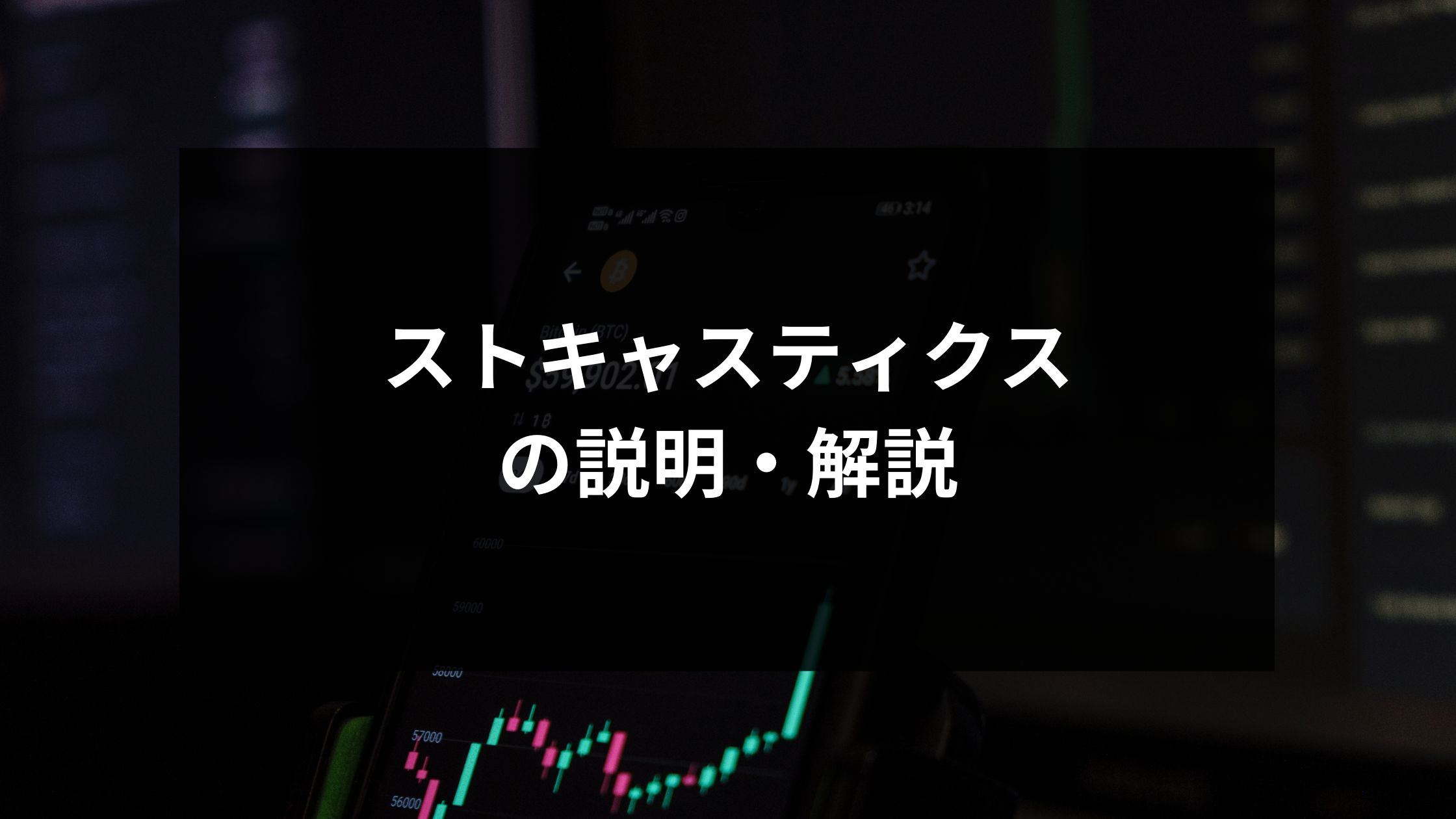





コメントを残す