FXのテクニカル分析は外国人が発案していることが多いのですが、日本人が発案したものも存在しています。
日本人が発案したテクニカル分析の1つが一目均衡表です。
今回は一目均衡表について、以下の内容に触れていきます。
- 一目均衡表とは
- 一目均衡表の見方
- 一目均衡表に存在する理論
- 一目均衡表の使い方
- 一目均衡表の注意点
一目均衡表について知りたかった方や一目均衡表の見方・使い方が知りたい方は、是非この記事を最後まで読んでみてください。
一目均衡表とは

株価を元に作られた一目均衡表は、1936年に日本人の細田悟一さんが考案したチャート分析の手法です。
価格・相場の変動を重要視している多数のテクニカル分析に対して、一目均衡表は時間を主軸にしているテクニカル分析です。
「買いと売りの均衡が崩れる方向に相場が動く」といった考えのもと作られたテクニカル分析となっています。
一目均衡表の見方

一目均衡表は以下4種類の線を使って見ていきます。
- 基準線
- 転換線
- 先行スパン
- 遅行スパン
基本的な線となる基準線・転換線に加えて先行スパン1・2と遅行スパンの4種類5本の線で見ることになります。
ここからは、上記一目均衡表4種類の線について、1つずつ詳しくお教えいたします。
基準線
過去26日間の相場の一番高い値と一番低い値の平均となる基準値を出します。
その基準値を結んでいってできたものが「基準線」と呼ばれるものになります。
この基準線が上を向いている場合強めに昇っており、下を向いている場合は落ちているという判断ができます。
転換線
26日と中期的に見える基準線に対して、9日と短期間の一番高い値と一番低い値の平均を繋げることでできる線を転換線と呼びます。
基準線と同じように線が上を向いていれば強めに昇っていて、下を向いていれば落ちている判断基準になります。
基準線の26や転換線の9は基本数値と呼ばれているもので、この数字は固定して使うものになります。
先行スパン
先行スパンは先行スパン1と先行スパン2の2本の線で、今現在の値動きが将来どのように影響するかを表したものです。
基準線・転換線の2本の線から平均値を算出しそれを26日先行して表示しているのが先行スパン1、過去52日で一番高い値と一番低い値の平均値を算出して26日先行して表示させてるのが先行スパン2です。
この先行スパン1と先行スパン2の間を塗りつぶして現れる帯状体になっている部分を「雲」と呼びます。
遅行スパン
その日の終値を26日前に遅行させて表示させるのが遅行スパンです。
当日の終値と26日前の終値の比較を可能にさせているものです。
この遅行スパンは一目均衡表内で一番大切な要素だと呼ばれています。
一目均衡表に存在する理論

一目均衡表には、以下のような3つの理論が存在しています。
- 時間論
- 波動論
- 水準論
上記3つの理論それぞれの側から一目均衡表を見ることで、取引に利用していくことができます。
これからは、上記の一目均衡表に存在する3つの理論について、より詳しい内容をお伝えいたしましょう。
時間論
時間側の視点から一目均衡表を分析していく、一番基礎的な重要視点となっているのが時間論です。
基準線に使われれている「26」や転換線に使う「9」に加えて「17」を基本数値とし、この数値を加減し組合せた「33」「42」「65」「76」を複合数値としています。
とある地点から基礎数値や複合数値の日数経過するタイミングに変動が発生しやすいという見解です。
波動論
チャートの波形形態を描写してそこから分析を行うのが波動論です。
形態には上がるだけ・下がるだけの「I波動」、上がり→下がり・下がり→上がりの「V波動」、上がり→下がり→上がり・下がり→上がり→下がりの「N波動」の3つがあり、これを使って分析します。
3つの形態のうちI波動とV波動が繰り返し推移していくことで、最後にはN波動になるようになっています。
水準論
上側の値と下側の値から次回の天辺と底辺を予測や分析していくのが水準論です。
値服観測論とも呼ばれているもので、目標の値を計算する時などに活用されています。
E計算値やV計算値・N計算値・NT計算値の4つの計算値を使って天辺と底辺を分析していくのが代表的ですね。
一目均衡表の使い方
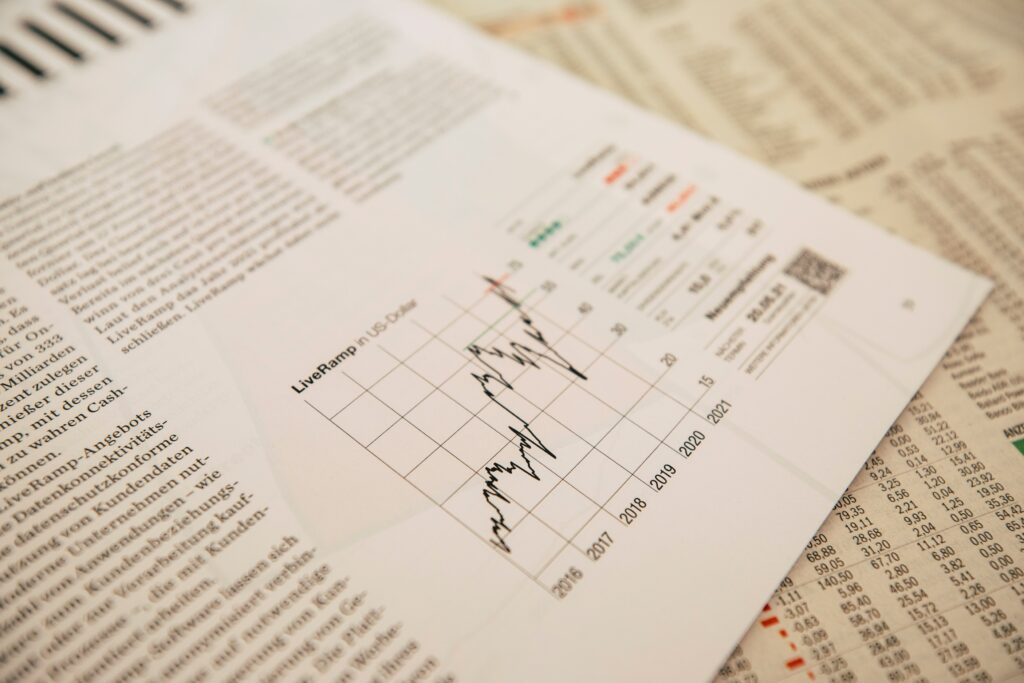
一目均衡表の使い方としては、以下の4通りが存在しています。
- 転換線と基準線を組み合わせる
- 先行スパン1と先行スパン2を組み合わせる
- 遅行スパン
- 三役好転
転換線・基準線を組み合わせる、先行スパン1・2を組み合わせる、遅行スパンのみそして特定の条件で起こる三役好転があります。
ここからは上記の一目均衡表の使い方4通りについて、順々にご説明いたします。
転換線と基準線を組み合わせる
転換線・基準線の2つを使って、他のテクニカル指標のようにゴールデンクロス・デッドクロスのような使い方が可能です。
転換線と基準線が交差して転換線が基準線を上に突き抜けたら、買いのサインとなるゴールデンクロスになります。
逆に転換線が基準線を下に突き抜けたら、売りのサインとなるデッドクロスになります。
このように転換線と基準線の2つがクロスするところが、相場が転換する目安になっていますね。
先行スパン1と先行スパン2を組み合わせる
先行スパン1と2の位置関係でトレンドを見ることができ、先行スパン1が上だと相場は上に昇っていて、先行スパン2が上だと相場は落ちていることになります。
他にも先行スパン1・2を組合せる使い方として、先行スパン1と2の間を塗って現れる帯状体「雲」とローソク足を利用します。
ローソク足が雲よりも下に推移している「上雲」と呼ばれるトレンドが昇っている状態と、逆に雲よりローソク足が上に推移している「下雲」と呼ばれるトレンドが落ちている状態があります。
遅行スパン
雲とローソク足だけでなく、遅行スパンとローソク足でシンプルに見る利用方法もあります。
遅行スパンがローソク足よりも上なら相場が強めとなり、下なら相場が弱めと判断できます。
遅行スパンがローソク足を上に突き抜ける場合、価格と共に遅行スパン自体が上がる傾向にあります。
三役好転
以下の3つが同時に発生した場合「三役好転」が起こります。
- 基準線を転換線が上に突き抜けている
- ローソク足を遅行スパンが上に突き抜けている
- 雲の上をローソク足が推移している
上記が揃うと「三役好転」となり、相場が強気な状態で続きやすくなり強力な買いサインだと判断できます。
ただし、3つ揃ってからエントリーした際にトレンドに乗れないことがあるので、条件が2つ揃ったところでエントリーを考えてダマシに引っかからないよう気をつけましょう。
一目均衡表の注意点

どのテクニカル分析においてもいえますが、ダマシは一目均衡表でも起こるので他のテクニカル分析と組合せて見るのが良いです。
また先行スパン1・2によってできる雲には上下関係が逆転する「ねじれ」が発生することがあり、これを価格が通過するとトレンドが変化しやすいです。
こうなると予想以上の激しい変動が発生するので、できれば取引を避けたほうがよいですね。
最後に

今回は日本人考案のテクニカル分析である一目均衡表について、見方や使い方・理論などをご紹介しました。
一目均衡表は4種類5本の線と、3つの理論でチャートを見ていくテクニカル分析です。
5本の線をそれぞれで組み合わせることで、トレンドの流れや強さを判断することが可能です。
「三役好転」が一番のチャンスとなりますが、ダマシもあるのでそういった部分には気をつけましょう。

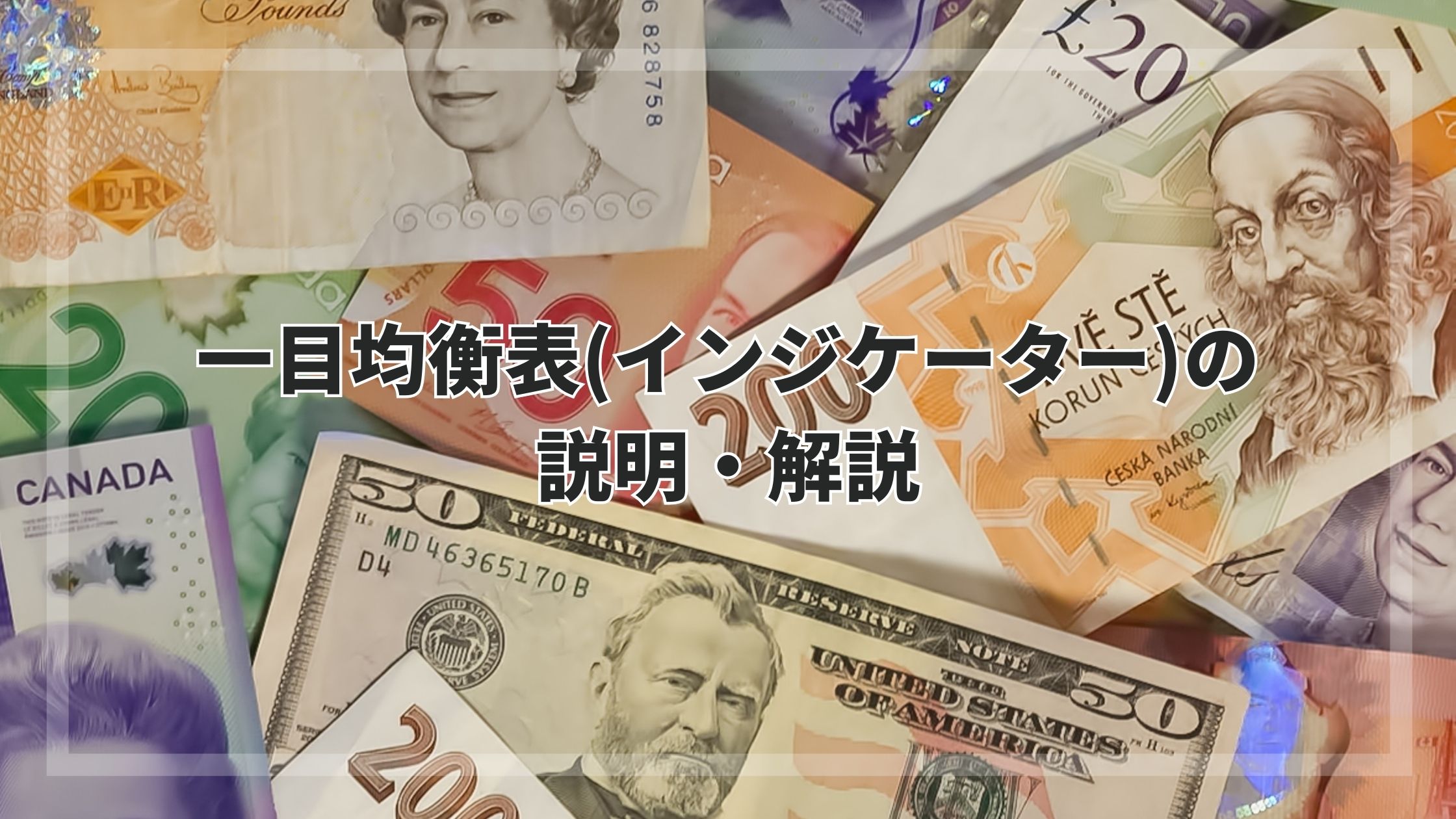
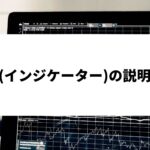




コメントを残す