FXのテクニカル指標には様々なものがありますが、中には価格自体を計算対象にしないようなものもあります。
今回はそんな価格自体を計算対象としないテクニカル指標RCIについて、以下のことをお教えいたします。
- RCIがなんなのか
- RCIの使い方について
- RCIとRSIの違いについて
- RCIの注意点について
RCIについて知りたかった方やRCI自体の使い方・RSIとの違いについて学びたかった方は、是非この記事を最後まで読んでみてください。
RCIとは

日本語で「順位相関指数」という意味の「Rank Correlation Index」の英語から、頭文字をとったのがRCIです。
価格そのものを計算対象にしている他のテクニカル指標に対して、時間・価格それぞれに順位付けを行い2つの相関関係を指標化したテクニカル指標となっています。
RCIは-100~+100の値で表され、価格が上がり続ければ+100に近くなっていく高値圏、下がり続ければ-100に近くなっていく安値圏と判定できます。
RCIの使い方

RCIの使い方としては、以下の3つが存在しています。
- 買いのサイン
- 売りのサイン
- ゴールデンクロス・デッドクロス
売り買いのサインに加えて、ゴールデンクロス・デッドクロスを利用する方法もあります。
ここからは、上記3つのRCIの使い方についてそれぞれより詳しくご説明していきます。
買いのサイン
RCIが0%ラインを通過しマイナスからプラス圏内へと突入した時は買いのサインとなります。
また底値圏から上へと昇っていって-80%より上へと昇った場合も買いのサインになりますね。
単純にマイナス圏で下がっていたラインが反発した時も、買いのサインだと判断して問題ないです。
売りのサイン
買いとはまったく逆となり、0%ライン通過後プラスからマイナス圏内へと突入した場合は売りのサインとなります。
高値圏にいたラインが下がっていって+80%よりも下に落ちた場合も、売りのサインだと判定できます。
こちらも単純にプラス圏で上がっていたラインが反発した際も、売りのサインだと受け取って問題ないです。
ゴールデンクロス・デッドクロス
RCIでは3本線を使ったゴールデンクロス・デッドクロスでも相場の分析をすることができます。
短期RCIラインが中期RCIラインを下から上へ突き抜けた場合は、買いのシグナルとなるゴールデンクロスになります。
逆に短期RCIラインが中期RCIラインを上から下に突き抜けた場合は、売りのシグナルとなるデッドクロスになります。
RCIとRSIの違い

RCIと同じようにオシレーター系インジケーターで名前もそっくりで見分けがつけにくい「RSI」というテクニカル指標が存在しています。
「時間」「価格」の2つに順位付けして相関関係を見るRCIに対して、RSIは一時的な上がりと下がりの比率にどれほど差ができたかを示す指標となっています。
レンジ相場であればRSIは効果が発揮されますが、トレンド相場になってしまうと有効性は低くなるデメリットがあります。
これに対してRCIはRSIほどの相場過熱感分析ができない代わりに、レンジ相場・トレンド相場の両方に対応することが可能といった違いがあります。
RCIの注意点

1本のラインでも見ることができるRCIですが、極力2本以上を使って見るようにしたほうが良いです。
2本以上のラインを使うことで1本の時より別の角度でみることが可能で、正確な相場分析ができます。
FXの分析には100%は存在していませんが、ちょっとでも正確に相場分析を行うことでより利益を高めることができます。
もちろんRCIにおいてもダマシは起こるので、RCIだけではなく他のテクニカル指標も合わせて利用することが大切です。
最後に

今回は価格自体を計算対象とせず、「時間」「価格」に順位をつけて相関関係を指標化するテクニカル指標RCIについてご紹介しました。
RCIは0%ラインを基準にした使い方に加えて、3本の線によるゴールデンクロス・デッドクロスを使った方法もあります。
RCIと似ているRSIですが、レンジ相場には強いRSIに比べてRCIはレンジ相場・トレンド相場の両対応になっている特徴があります。
RCIでもダマシなどは発生するので、単体で使うのではなく他のテクニカル指標と組み合わせて見ていくことが大事です。

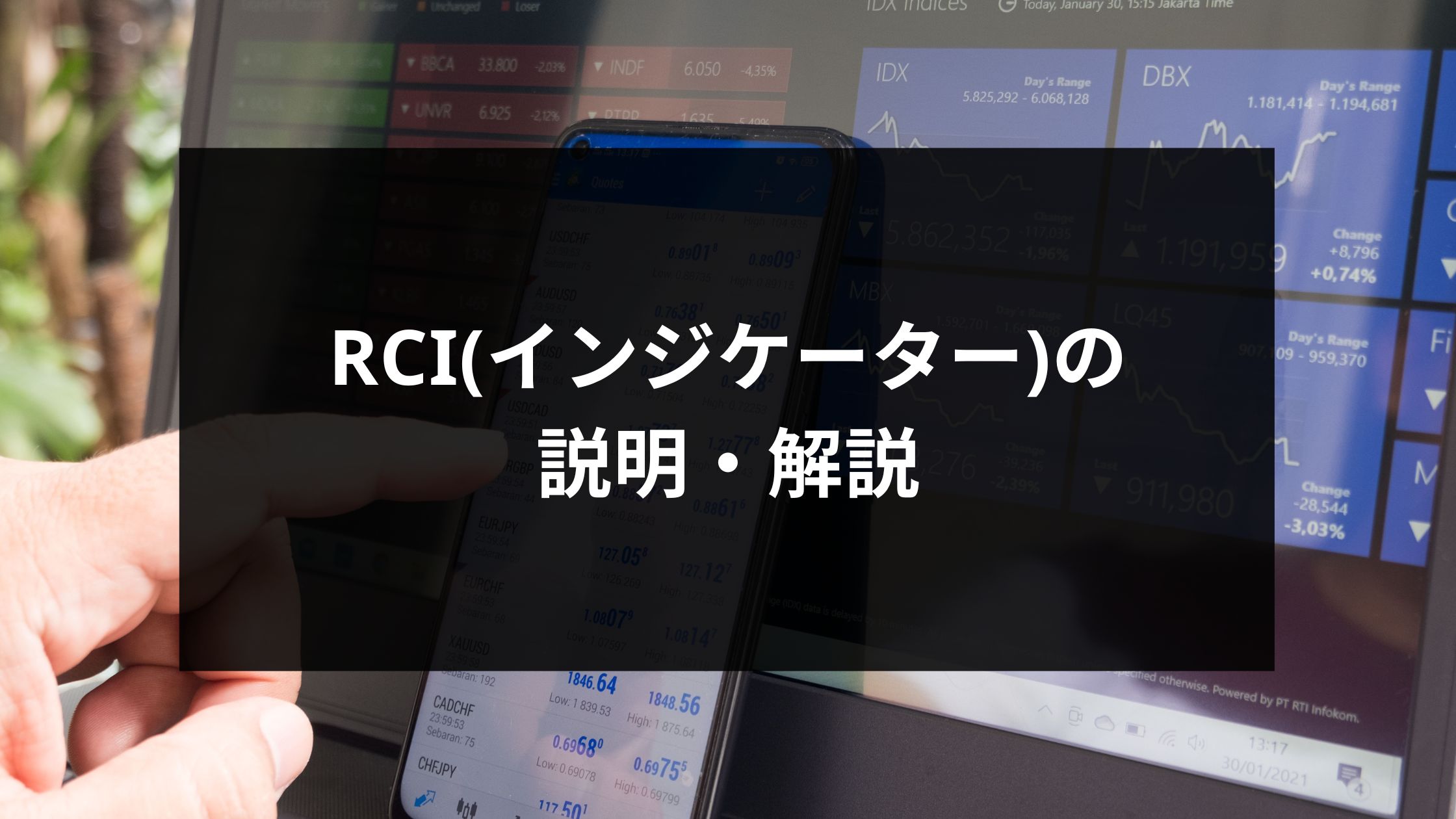

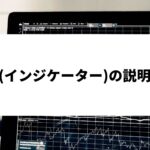



コメントを残す